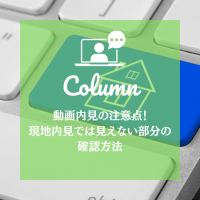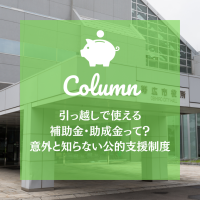水害リスクの高い賃貸物件を見抜く3つのポイント!安全な住まい選びに必要な要素とは?
近年、気候変動の影響で、日本各地で水害が頻発しています。大切な住まい選びにおいて、水害リスクを考慮することは、もはや不可欠な要素と言えるでしょう。特に、賃貸物件を探す際には、将来的な安全性を確保するためにも、水害リスクをしっかりと見抜く知識が求められるでしょう。この記事では、これから賃貸物件探しをする方々に向けて、水害リスクの高い物件を見抜くための具体的な方法を解説します。ハザードマップの読み解き方から、地盤情報のチェック、そして内見時の注意点まで、安全な住まい選びのための羅針盤となる情報を提供します。
ハザードマップから見抜く

水害リスクを把握するための最も基本的なツールは、ハザードマップです。ハザードマップとは、過去の浸水実績や地形データなどを基に、各自治体が作成する水害予測地図のこと。ハザードマップを見ることで、物件周辺の浸水想定区域や浸水深、土砂災害警戒区域など、その土地が持つ水害のリスクを具体的に示してくれます。
ハザードマップは、各自治体のウェブサイトや窓口で入手できるほか、国土交通省が運営する「ハザードマップポータルサイト」でも閲覧可能です。
ハザードマップを読み解く際のポイントは以下の通りです。
浸水想定区域と浸水深
まず確認したいのは、物件が浸水想定区域に含まれているかどうか、そして、もし含まれている場合、どの程度の浸水が想定されるかという点です。浸水深は、私たちの暮らしに直接的な影響を与える重要な情報です。浸水深が深いほど、家財の損失だけでなく、命の危険性も高まります。
「まさか、私の住む場所が浸水するなんて…」そう思われる方もいるかもしれません。しかし、近年、都市部でも想定を超える浸水被害が多発しています。だからこそ、他人事と思わず、ハザードマップでしっかりと確認することが大切です。
土砂災害警戒区域
次に確認したいのは、土砂災害警戒区域です。もし物件がこの区域に含まれている場合、大雨や地震の際に、土砂崩れや地すべりなどの危険性があります。特に、山の近くや傾斜地にある物件を検討している場合は、注意が必要です。
「土砂災害」と聞くと、山間部だけの話だと思われがちです。しかし、都市部でも、崖の近くや傾斜地では、土砂災害のリスクがあります。ハザードマップで、あなたの住む場所が土砂災害警戒区域に含まれていないか、必ず確認しましょう。
過去の浸水実績
過去に浸水被害が発生したことがある場所は、再び浸水する可能性が高いということを覚えておきましょう。ハザードマップには、過去の浸水実績も記載されています。過去の記録は、未来を予測するための重要な手がかりとなります。
「過去に一度でも浸水したことがある場所は、要注意」この言葉を胸に刻み、安全な住まいを選びましょう。
避難場所と避難経路
最寄りの避難場所と避難経路を確認しておきましょう。いざという時、安全に避難できる場所と経路を事前に把握しておくことは、非常に重要です。
「避難場所なんて、まだ先の話…」そう思われるかもしれません。しかし、災害はいつ起こるか分かりません。だからこそ、日頃から避難場所と避難経路を確認し、いざという時に備えておくことが大切です。
地盤情報から見抜く

ハザードマップで大まかな水害リスクを把握したら、次に確認したいのは地盤情報です。地盤は、私たちの生活を支える土台であり、その性質は水害リスクに大きく影響します。安全な住まいを選ぶためには、足元からしっかりと情報を集めることが大切です。
地盤情報は、少し専門的な知識が必要となるため、難しく感じるかもしれません。しかし、心配はいりません。各自治体のウェブサイトや図書館で入手できる資料、そして国土交通省が運営する「国土地盤情報検索サイトKuniJiban」を活用すれば、誰でも簡単に地盤情報を調べることができます。
では、地盤情報からリスクを見抜く3つの要素についてご紹介します。
標高
まず確認したいのは、物件の標高です。一般的に、標高が低い場所は、川や海が近く、浸水しやすい傾向があります。一方、標高が高い場所は、浸水リスクが低いと考えられます。
「標高が高いから安心」と安易に考えるのは危険です。標高が高くても、急な斜面や崖の近くは、土砂災害のリスクがあります。標高だけでなく、周辺の地形と合わせて確認することが大切です。
地盤の種類
次に確認したいのは、地盤の種類です。地盤は、その成り立ちによって、軟弱地盤と強固地盤に分けられます。
- 軟弱地盤:
- 沖積低地や谷底平野など、比較的新しい堆積物で構成された地盤です。
- 水分を多く含みやすく、地盤が緩いため、浸水や液状化のリスクが高いです。
- 強固地盤:
- 台地や段丘など、古い地層で構成された地盤です。
- 地盤が固く、安定しているため、浸水や液状化のリスクが低いと考えられます。
「軟弱地盤だから絶対にダメ」と決めつける必要はありません。軟弱地盤でも、適切な地盤改良工事を行えば、安全な住まいを建てることができます。しかし、地盤改良には費用がかかるため、事前に確認しておくことが大切です。
過去の液状化被害
過去に液状化被害が発生したことがある場所は、再び液状化する可能性が高いということを覚えておきましょう。液状化は、地震の際に、地盤が液体状になる現象です。建物の倒壊や地盤沈下を引き起こす可能性があり、非常に危険です。
「液状化なんて、遠い場所の話」と思われがちですが、都市部でも液状化被害が発生する可能性があります。過去の液状化被害を確認し、安全な場所を選びましょう。
内見時に見抜く
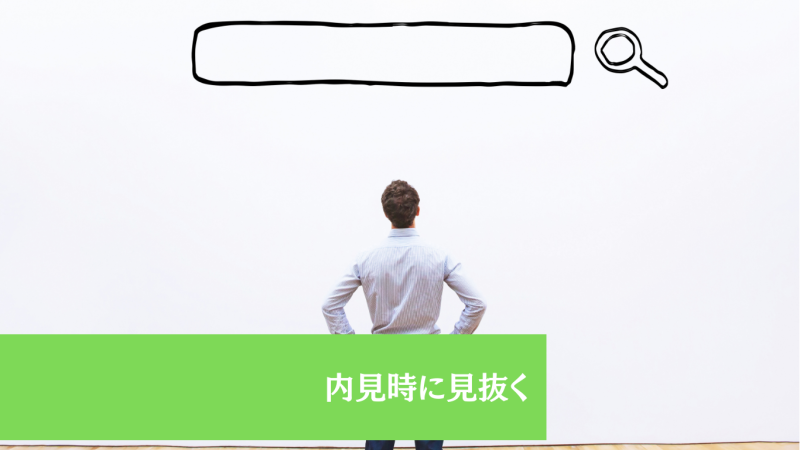
ハザードマップや地盤情報で水害リスクの可能性を把握したら、いよいよ内見です。内見は、あなたの目で物件の安全性や周辺環境を確かめる絶好の機会です。ハザードマップや地盤情報だけでは分からない、物件の細かな部分までチェックし、安全な住まいを選びましょう。
周辺の地形
まず、物件周辺の地形を注意深く観察しましょう。川や海に近い場所、低い土地、傾斜地などは、水害リスクが高い傾向があります。
「川のせせらぎが聞こえる素敵な物件」と思っても、大雨が降ると川が氾濫する危険性があります。「眺めの良い高台の物件」と思っても、土砂災害のリスクがあるかもしれません。物件周辺を歩き、地形をしっかりと確認しましょう。
建物の構造
次に、建物の構造を確認しましょう。一般的に、鉄筋コンクリート造や鉄骨造は、木造よりも浸水に強い傾向があります。また、1階よりも2階以上の部屋を選ぶことで、浸水リスクが軽減可能です。
「おしゃれなデザイナーズ物件」と思っても、木造で1階の部屋は、浸水した場合に大きな被害を受ける可能性があります。建物の構造をしっかりと確認し、安全性を確かめましょう。
浸水対策
建物に浸水対策が施されているか確認しましょう。止水板や排水ポンプなどが設置されている物件は、浸水被害を軽減できる可能性があります。
「止水板や排水ポンプなんて、大げさな…」と思うのは危険。近年、都市部でも浸水被害が多発しています。備えあれば憂いなしです。浸水対策が施されている物件は、あなたの安心感を高めてくれるでしょう。
周辺の水路や排水設備
周辺の水路や排水設備の状態を確認しましょう。水路が詰まっていたり、排水設備が不十分な場合、大雨が降ると水が溢れ、浸水リスクが高まります。
「水路なんて、普段は気にも留めない…」と思わないでください。大雨が降ると、水路は重要な役割を果たします。水路や排水設備の状態を確認し、水はけの良い場所を選びましょう。
過去の浸水痕跡
建物の壁や床などに、過去の浸水痕跡がないか確認しましょう。過去に浸水被害があった物件は、再び浸水する可能性が高いです。
また、壁や床のシミは、過去の浸水痕跡かもしれません。不動産会社に確認し、過去の浸水被害について詳しく聞いてみましょう。
不動産会社への質問
最後に、不動産会社に、過去の浸水被害や周辺のハザード情報について質問しましょう。不動産会社は、重要な事項を説明する義務があります。
信頼できる不動産会社は、あなたの安全を第一に考えています。積極的に質問し、プロの意見を聞きましょう。
まとめ
水害リスクは、決して他人事ではありません。近年、都市部でも水害被害が多発しており、誰もが水害に遭う可能性があります。大切な住まいを守るためにも、水害リスクに関する知識を身につけ、安全な住まいを選びましょう。もし、水害リスクについて不安な点や疑問点があれば、住まいのプロである不動産会社に相談してみましょう。