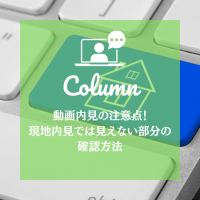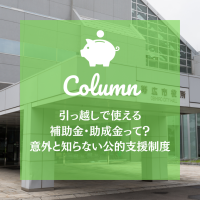公営住宅の申し込み方法と入居条件とは?公営住宅以外の選択肢についても解説
経済的な理由で部屋探しに困っている人にとって、家賃が割安な公営住宅は心強い選択肢の一つです。しかし、公営住宅は誰でも入居できるわけではなく、申し込み方法や入居条件などが定められています。この記事では、公営住宅の概要から申し込み方法、入居条件、さらには公営住宅以外の選択肢まで詳しく解説します。
公営住宅とは?

公営住宅とは、地方公共団体が建設・借り上げ・運営する賃貸住宅のこと。一般的な賃貸住宅よりも家賃が安く、経済的な負担を軽減できるのが特徴です。市営住宅、県営住宅、都営住宅と呼ばれるものの総称として、公営住宅と呼ばれています。
公営住宅は家賃が安く支援が受けられる場合もある

ポイントは、入居者の収入に合わせて家賃が設定されるという点です。物件の規模や立地にも左右されますが、同じ物件に住む家庭でも家賃が異なるケースがあります。極端な話、同じ建物でも家賃1万円の部屋もあれば、家賃6万円の部屋もあるでしょう。
さらに、収入に応じて家賃が段階的に上がる仕組みになっているのも、知っておきたいポイントです。
いずれにおいても、一般的な賃貸物件よりも家賃が割安傾向にあります。加えて、障がい者や母子父子家庭、高齢者などで、収入が一定額以下の場合は家賃の減免措置が受けられるのもメリットです。具体的な基準は各自治体によって異なるため、居住する自治体の窓口に確認すると良いでしょう。
公営住宅の入居条件とは

公営住宅の入居条件は、地方公共団体によって異なりますが、一般的には以下の条件を満たす必要があります。
- 住宅に困窮していること
- 収入が一定基準以下であること
- 同居親族がいること(単身者向けの住宅は別途条件あり)
- 地方公共団体の条例で定める要件を満たすこと
公営住宅に応募するには、政令で定められている収入要件や、各自治体で設けられた要件をすべて満たす必要があります。これらは、居住する地域の自治体によって細かく定められており、収入基準だけでなく、家族構成や居住年数、在住・在勤要件、過去の家賃滞納歴などが考慮される場合もあります。
そのため、居住地の自治体の公営住宅に関する情報を事前に確認することが重要です。
また、募集時期も自治体によって年数回行われる場合や、空きが出た際に随時募集される場合などがあり、定期的な情報収集が欠かせません。
公営住宅におすすめな人

公営住宅は、以下のような人におすすめです。
- 経済的に困窮しており、家賃の支払いが難しい人
- 高齢者や障害者など、住宅の確保が困難な人
- 子育て世帯など、住宅の広さや安全性が必要な人
- 災害などで住宅を失った人
公営住宅の申し込み方法とは
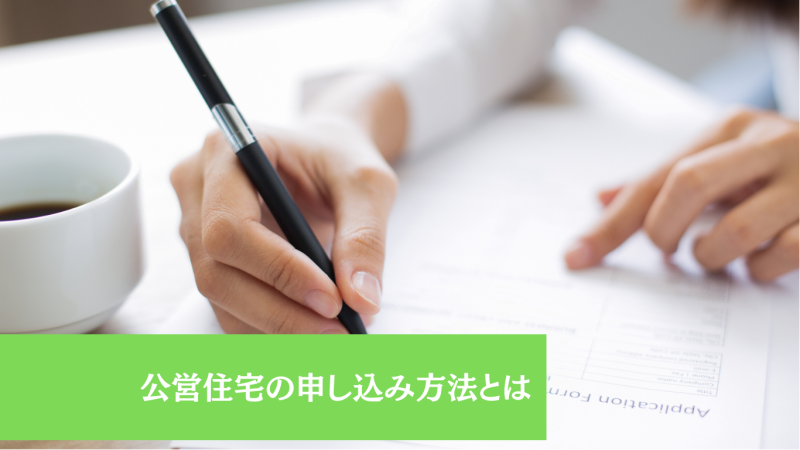
公営住宅の申し込み方法は、地方公共団体によって異なります。一般的には、以下の手順で申し込みます。
①地方公共団体の住宅課などで入居募集の情報を確認する
②申し込みに必要な書類を入手する
③必要事項を記入し、必要書類を添付して申し込む
④抽選や選考の結果を待つ
⑤入居が決まったら、契約手続きを行う
申し込みは、年に数回、募集期間が設けられています。募集期間や申し込み方法は、地方公共団体のウェブサイトや広報誌などで確認できます。
※とはいえ、入居申し込みをしても抽選となるケースが多いため、必ずしも入居できるとは限りません。
経済的不安がある人は公営住宅以外の選択肢も
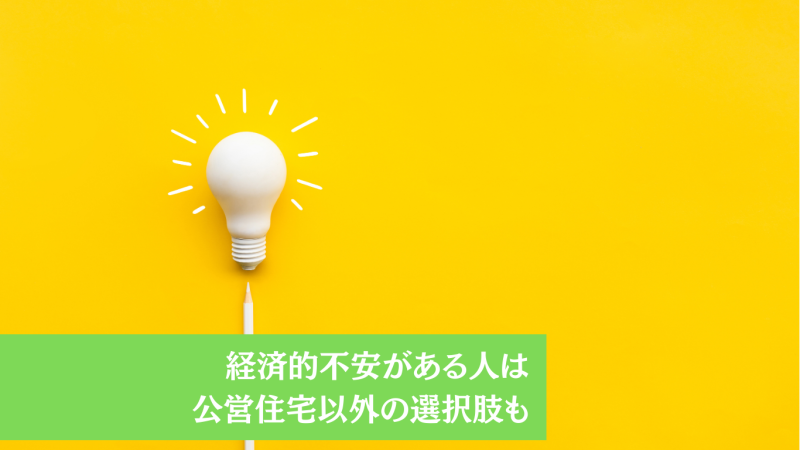
経済的に不安がある場合、公営住宅以外にもさまざまな選択肢があります。
住宅確保給付金の利用
住宅確保給付金は、離職や廃業などで経済的に困窮し、住宅を失うおそれのある人を対象に、家賃相当額を支給する制度です。支給額や支給期間は、自治体によって異なります。
ひとり親家庭等家賃助成の利用
ひとり親家庭や所得の低い高齢者世帯などを対象に、家賃の一部を助成する制度です。助成額や助成期間は、自治体によって異なります。
たとえば横浜市には「子育てりぶいん」という支援制度が設けられており、民間の既存住宅を家賃補助付き賃貸住宅に認定し、最大4万円、最長6年間の家賃補助を行っています。
住宅セーフティネット制度の利用
住宅セーフティネット制度は、高齢者や障害者、子育て世帯など、住宅の確保が困難な人を対象に、安全・安心な賃貸住宅を提供する制度です。登録された住宅は、家賃の減額や入居の優先など、さまざまな支援が受けられます。
くわしくは、本サイトの「賃貸住宅共有促進法(住宅セーフティネット制度)とは一体何?利用対象や利用方法をご紹介」でも紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
UR賃貸と公社賃貸との違い
公的な賃貸住宅としては、UR賃貸住宅や公社賃貸住宅もあります。それぞれの違いは以下の通りです。
【UR賃貸住宅】
独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)が管理・運営する賃貸住宅。礼金・仲介手数料・更新料・保証人が不要で、初期費用を抑えて入居できるのが特徴です。
【公社賃貸住宅】地方住宅供給公社が管理・運営する賃貸住宅。地域によって入居条件や家賃などが異なります。
UR賃貸住宅は、一定の所得がある方向けの賃貸住宅であり、公営住宅とは対象者が異なります。公社賃貸住宅は、地域によって対象者や条件が異なるため、確認が必要です。
特定優良賃貸との違い
UR賃貸住宅と特定優良賃貸住宅(特優賃)は、どちらも公的な賃貸住宅ですが、運営主体や対象者、家賃補助の有無などに違いがあります。
【UR賃貸住宅】
- 独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)が運営
- 礼金・仲介手数料・更新料・保証人が不要
- ファミリー向けから単身者向けまで幅広い物件がある
- 所得制限があるが、特優賃よりは緩やか
- 家賃補助はない
【特定優良賃貸住宅】
- 国や自治体から補助を受けた民間事業者などが運営
- 中堅所得者向けの賃貸住宅
- 家賃補助がある(期間や金額は物件によって異なる)
- UR賃貸住宅よりも所得制限が厳しい場合が多い
- ファミリー向けの物件が多い
おもな違いは、運営元や対象者が違うという点、家賃補助の有無です。どちらが適しているか、というのは家族構成や収入、希望条件などによって異なります。
公営住宅に入居する際の注意点
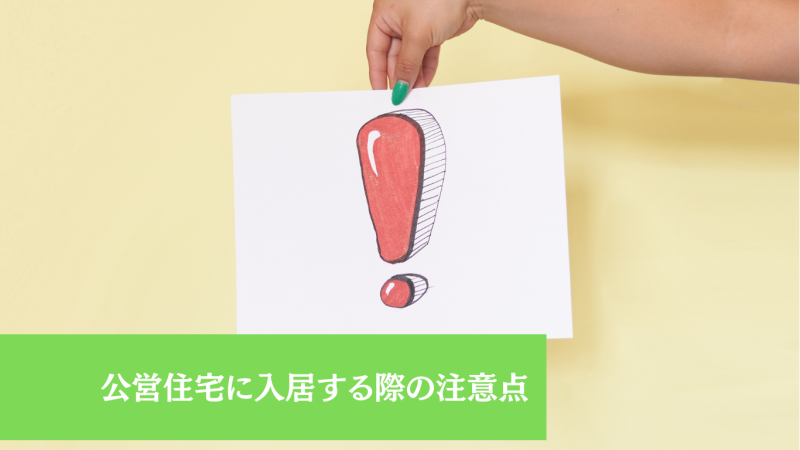
公営住宅は、経済的に困窮している方々にとって非常に魅力的な住居選択肢ですが、入居にあたってはいくつかの注意点があります。
ペットの飼育ができない
多くの公営住宅では、ペットの飼育が禁止されています。これは、ほかの入居者への配慮や、建物の衛生管理上の理由からです。ペットを飼育している方は、入居前にペットの預け先や、ペット可の物件への引っ越しを検討する必要があります。
家賃滞納で強制退去となる
公営住宅は、低家賃で提供されていますが、当然家賃の支払いは義務です。滞納が続くと、強制退去となる場合があります。
経済的に不安がある場合は、早めに自治体の住宅課などに相談し、家賃の減免制度や支払い計画について相談しましょう。
また、近年では、高齢者や障害者、子育て世帯など、特に配慮が必要な入居者に対して、家賃の減免や支払い猶予などの支援制度を設けている自治体もあります。これらの制度を積極的に活用すれば、安心して公営住宅での生活を送ることができるでしょう。
まとめ
公営住宅は、経済的に困窮している人にとって、安心して生活できる住まいを提供する重要な役割を担っています。しかし、入居条件や申し込み方法などが定められているため、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。また、公営住宅以外にもさまざまな選択肢があるため、自分に合った制度を活用して、安心して生活できる住まいを見つけましょう。