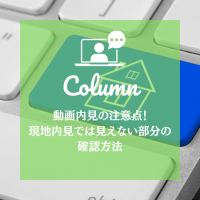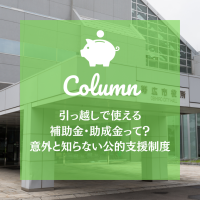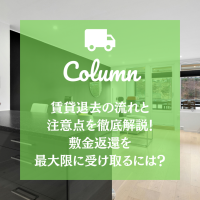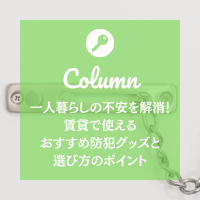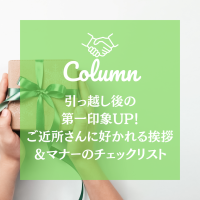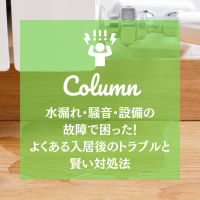賃貸物件の「孤独死」対策と、もしもの時の備え
近年、社会問題としても注目されている「孤独死」。賃貸物件においても、借りる側、貸す側の双方にとって、この問題は決して無視できない課題となっています。しかし、不安に感じるばかりではなく、適切な知識と対策を知っておくことで、孤独死のリスクを減らし、もしもの時に備えることができます。このコラムでは、賃貸物件における孤独死の現状から、具体的な予防策、そして万が一の事態にどう対処すべきかまでを、多角的に解説していきます。
孤独死を取り巻く現状と賃貸物件への影響
「孤独死」という言葉は、誰にも看取られることなく、自宅で亡くなることを指すのが一般的です。特に単身高齢者の増加、核家族化の進行、地域コミュニティの希薄化などが背景にあり、都市部を中心にその数は増え続けていると言われています。
賃貸物件において孤独死が発生した場合、それは単に一人の命が失われたという悲しい出来事にとどまりません。物件の貸主にとっては、特殊清掃やリフォームにかかる費用、長期間にわたる空室、そして次の入居者を見つける際の風評被害など、経済的・精神的に大きな負担が生じます。また、同じ建物に住む他の入居者にとっても、心理的な影響は小さくありません。
借りる側である私たちも、自身の問題として捉え、積極的に対策を講じることが、安心して賃貸生活を送る上で非常に重要です。
個人の取り組みと社会的なサポートで孤独死を未然に防ぐ

孤独死は、孤立が深まることでリスクが高まります。日頃からのちょっとした心がけや、利用できるサービスを知っておくことが、予防の第一歩となります。
日常的なコミュニケーションの維持
最も基本的な対策は、人とのつながりを保つことです。家族や友人との定期的な連絡はもちろんのこと、近所付き合いも大切にしましょう。
たとえば、家族・友人との連絡頻度を決めること。毎日でなくとも、週に一度など、定期的に連絡を取り合う習慣を作りましょう。特に高齢の方や持病をお持ちの方は、離れて暮らす家族に安否確認をお願いしておくのも良い方法です。
そして、近所付き合いを大切にすることも重要です。 地域のイベントに参加したり、挨拶を交わしたりするだけでも、いざという時に異変に気づいてもらえる可能性が高まります。回覧板の受け渡しや、ゴミ出しの際に顔を合わせるだけでも、安否確認の一助になります。
さらに、趣味のサークルやボランティア活動に参加するのもポイントです。外出する機会を増やし、社会との接点を持つことは、心身の健康を保つ上でも非常に有効です。新しい出会いを通じて、孤独感を軽減できます。
民間や自治体の見守りサービスを利用する
近年では、孤独死を防ぐための多様な見守りサービスが提供されています。これらを活用することも有効な手段です。
たとえば、電気・ガス・水道の使用状況による見守り。 電力会社やガス会社などが提供するサービスで、一定期間使用量が変化しない場合に異常を感知し、家族や指定の連絡先に通知するものです。
また自宅内の人の動きを感知する人感センサーや、体調不良時に押すことで緊急連絡先に繋がるボタンなどを導入する方法です。これらは、高齢者向けの賃貸物件や、一部の住宅では標準装備されている場合もあります。
そして、配食サービスや訪問介護など、定期的に自宅を訪れるサービスを利用することで、自然な形で安否確認が行われます。食事の準備が難しい方や、身体的なサポートが必要な方にとっては、生活支援と見守りを兼ねられるため一石二鳥です。
このほかにも、各自治体では高齢者や障がい者などを対象に、地域包括支援センターや民生委員による定期訪問、電話での安否確認、緊急通報システムなどの見守りサービスを提供している場合があります。居住地の自治体窓口に問い合わせてみましょう。
健康管理と異変への早期対応
日頃から自身の健康状態に意識を向けることも重要です。
たとえば、定期的な健康診断の受診。自身の体の状態を把握し、早期に病気を発見・治療することは、重篤な状態になるリスクを減らします。
また持病がある人は、医師の指示に従い、薬を忘れずに服用するなど、持病の管理を徹底しましょう。
少しでも体調に異変を感じたら、かかりつけ医や地域の医療機関にすぐに相談するように心がけるのも大切です。「これくらいなら大丈夫」と無理をせず、早めに受診しましょう。
万が一に備えて賃貸契約と保険を確認する

万が一の事態に備え、賃貸契約の内容や加入している保険について確認しておくことも、安心して賃貸生活を送る上で非常に重要です。
賃貸借契約書の確認と緊急連絡先の指定
賃貸借契約書には、契約に関する重要な事項だけでなく、緊急時の対応についても記載されている場合があります。
契約時に、連帯保証人とは別に緊急連絡先として、家族や親族の情報を求められるケースがほとんどです。この緊急連絡先は、入居者本人に何かあった際に、管理会社や大家さんがまず連絡を取る先となります。定期的に連絡が取れる人、信頼できる人を指定し、その人にも事前に承諾を得ておくことが重要です。
また、契約書には孤独死が発生した場合の原状回復や、残置物の処理に関する特約が記載されているケースもあります。入居時にしっかり確認し、不明な点があれば不動産会社に質問しておきましょう。
保険の加入状況の確認
火災保険には、特約として「個人賠償責任保険」や「家財保険」が付帯していることが多いです。これらは、孤独死が発生した場合の費用負担にも関係してくる可能性があります。
個人賠償責任保険
もし自身が原因で建物や他人に損害を与えてしまった場合に補償される保険です。直接孤独死に起因するものではありませんが、例えば、死後しばらくして設備の故障などにより水漏れが発生し、階下に損害を与えてしまった場合などに適用される可能性があります。
家財保険
自身の家財道具が火災や水災などで損害を受けた際に補償される保険です。孤独死に伴い部屋が汚損し、家財の処分が必要になった場合など、一部補償の対象となる可能性もあります。保険会社に具体的に確認してみましょう。
遺品整理費用特約・孤独死保険特約
近年では、賃貸物件向けに孤独死が発生した場合の清掃費用や残置物撤去費用などをカバーする特約や、専門の保険商品も登場しています。特に高齢者や単身者で入居を検討している場合は、こうした保険の加入を検討してみるのも良いでしょう。
遺言書やエンディングノートの作成
万が一の事態に備え、自身の財産や持ち物、デジタルデータの扱い、そして死後の希望などを記した遺言書やエンディングノートを作成しておくことも有効です。これにより、残された家族がスムーズに手続きを進めることができ、賃貸物件における残置物の問題なども軽減されます。
- 遺言書…法的な効力を持つもので、財産の分配や遺品整理の方針などを明確に示せます。
- エンディングノート…法的な効力はないものの、家族へのメッセージ、連絡先、銀行口座の情報、SNSアカウントの情報、葬儀の希望、ペットの世話など、多岐にわたる情報を自由に書き残すことができます。これがあるだけでも、家族の負担は大きく軽減されます。
不安を軽減し、前向きな対策を
「孤独死」という言葉は重く、不安を覚えるかもしれません。しかし、これは決して他人事ではなく、誰もが直面しうる社会的な課題です。大切なのは、この問題を避けて通るのではなく、正しい知識を持ち、前向きに対策を講じることです。
日々のコミュニケーションを大切にし、利用できる見守りサービスを活用し、そして万が一の備えとして賃貸契約や保険の内容を確認する。これらは、孤独死のリスクを減らすだけでなく、私たち自身の安心感、そして周囲の人々とのつながりを深めることにも繋がります。