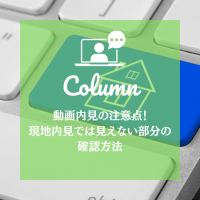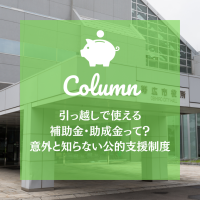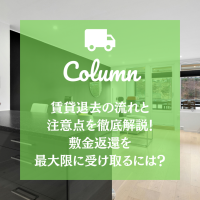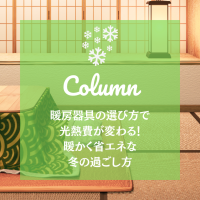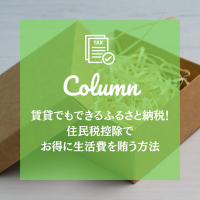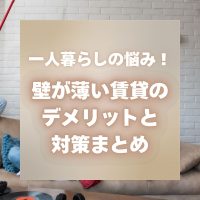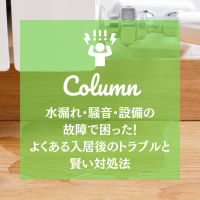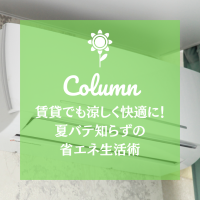暮らしをカスタマイズ!DIY可能な賃貸物件の探し方と注意点
「賃貸だから仕方がない」
「壁紙の色や設備が好みじゃないけど我慢するしかない」
…そう諦めていませんか?近年、入居者が自分の手で部屋をカスタマイズできる「DIY可能物件」が注目を集めています。画一的な賃貸物件ではなく、自分の個性やライフスタイルに合わせて内装を変えられるDIY物件は、住まいに対する満足度を格段に高めてくれます。
しかし、DIY可能な賃貸物件は、まだ一般的ではないため、「どうやって探せばいいの?」「どこまでやっていいの?」と疑問に思う方も多いでしょう。このコラムでは、DIY物件の賢い探し方から、契約前に必ず確認すべき注意点、そしてトラブルを避けるための心構えまでを詳しくご紹介します。
DIY可能物件のメリットと物件の特徴

DIY物件を探し始める前に、その魅力と、どのようなタイプの物件があるのかを理解しておきましょう。
DIY可能物件の大きなメリット
最大の魅力は初期費用を抑えつつ、理想、の空間を創造できる点です。
オーナー側が「現状回復不要」や「入居者が手を加えることを前提」としている物件が多いため、内装が古かったり、あえて最低限の状態で提供されていたりすることがあり、比較的家賃が抑えられているケースがあります。
また、入居者自身で壁紙を張り替えたり、棚を設置したりすることで、本来ならリフォームが必要な部分を低コストで改善できます。入居者側の視点で見れば、契約時の初期費用が抑えられるということです。
さらに、契約内容によりますが「現状回復義務がない」または「DIYした部分はそのまま」といった特約がある場合、退去時に高額な修繕費を請求されるリスクを減らせます。
知っておきたいDIY物件の3つのタイプ
「DIY可能」と一言でいっても、その自由度には幅があります。主に以下の3つのタイプがあります。
原状回復不要型(全面DIY可能型)…壁の撤去や間取りの変更など、構造に関わらない範囲であれば、比較的自由にカスタマイズが可能です。退去時の原状回復義務が免除されることが多い、最も自由度の高いタイプです。
部分DIY可能型(カスタマイズ型)…壁紙の張り替え、ペンキ塗り、棚の設置、床材の変更など「現状回復を要するが、一定の範囲内でDIYを許可する」タイプです。作業内容や使用する資材について、事前にオーナーや管理会社の許可が必要です。
付加価値型(設備変更許可型)…許可された設備のみ変更可能で、内装の大きな変更はできません。例えば、「照明器具の交換は自由」「コンロの交換は可」など、軽微なカスタマイズに限られます。
DIY物件の賢い探し方と検索キーワード
DIY可能物件は、通常のポータルサイト検索では見つけにくいことがあります。以下のキーワードや方法を試してみてください。
ポータルサイトでの複合検索
通常のフリーワード検索に、以下のキーワードを組み合わせて検索してみましょう。
【キーワード例】
- 「DIY可能」
- 「カスタマイズ可能」
- 「現状回復不要」
- 「フリーリノベーション」
- 「セルフリノベ」
ただし「ペット可」のように定型化された項目ではないため、不動産会社やオーナーによって表記が揺れていることがあります。「リノベーション」や「コンバージョン」といった言葉に隠れている場合もあるため、広い視点で検索することが大切です。
不動産会社への「直球」問い合わせ
最も確実な方法は、不動産会社に直接問い合わせることです。特に、地元密着型の不動産会社はオーナーと直接取引しているため、サイトには掲載されていないDIY相談可能な物件を知っていることがあります。
単に「DIY物件」と聞くだけでなく、「壁紙の張り替えと棚の設置をしたい」など、具体的な要望を伝えることで、オーナーに交渉できる物件を探してくれる可能性が高まります。
SNSや専門サイトでの情報収集
SNSや、DIY物件に特化したWebサイト、地域密着型の不動産屋のブログなどには、一般のポータルサイトには載らない情報が集まっています。
Instagramの活用例として「#DIY賃貸」「#セルフリノベーション」といったハッシュタグをフォローし、物件情報やリフォーム事例を探すことで、DIYに理解のある不動産アカウントを見つけられます。
契約前に必ず確認すべき「DIYのルール」

「DIY可能」という言葉を鵜呑みにするのは危険です。契約書には必ず目を通し、以下のルールを明確にしておきましょう。
「どこまでやっていいか」の明確化
最も重要なのが、DIY可能な範囲を明確に線引きすることです。
【OKなことの確認】
- 壁紙の張り替え(糊付けは可か、貼って剥がせるタイプ限定か)
- 釘打ちの可否
- 床材の変更
- 塗装の可否
…など、具体的な作業内容をリストアップして確認しましょう。
【NGなことの確認】
- 構造に関わる部分(壁の撤去、配管の変更など)
- 火災報知器などの設備の移動
- 共有部分への影響
…など、絶対にやってはいけないことを明確にしてください。
退去時の「原状回復義務」の確認
DIY物件の大きな魅力の一つが「原状回復義務の免除」ですが、これは物件によって異なります。
たとえば「特約」。 DIYした部分はすべて現状回復不要なのか、壁紙など指定された部分のみ現状回復不要なのか、すべて現状回復が必要だが、作業は許可するのかを、契約書で確認します。
また、自分で取り付けた設備や棚などを残置して良いか、それともすべて撤去する必要があるのかも、重要な確認事項です。
DIY資材や費用に関する取り決め
使用する資材や費用についても、事前に確認しておきましょう。
たとえば資材の場合。塗料の色や壁紙の素材など、オーナーや管理会社から指定があるかを確認します。特に、内装の安全性や建物の統一感を保つために、特定の資材の使用を義務付けられることがあります。
また、DIYにかかる費用は基本的に入居者負担ですが、たとえば「新しい壁紙代はオーナーが一部負担する」といった費用に関する交渉が可能かどうかも確認してみましょう。
ルールとマナーを守って、理想の住まいを創造しよう
DIY可能な賃貸物件は、自分の「理想の暮らし」を妥協なく実現できる素晴らしい選択肢です。しかし、そこには必ず「ルールとマナー」が伴います。
物件を探す段階で具体的な要望を伝え、契約時には「どこまでがOKで、どこからがNGか」「退去時にどこまで回復が必要か」というルールを明確にすることが、オーナーとの良好な関係を保ち、トラブルなく賃貸ライフを謳歌するための鉄則です。
ルールとマナーを守りながら、個性あふれる、世界に一つだけの住まいを創造してください。